療育におけるソーシャルストーリーとは?期待できる効果や実施方法について紹介
コラム
2023/12/19

福祉の仕事について調べていると、時折目にする「ソーシャルストーリー」という言葉。詳しく知りたいという人の為に、ソーシャルストーリーとは何か、その効果と実施方法を詳しく解説していきます。
もくじ
ソーシャルストーリーとは

ソーシャルストーリーとは、キャロル・グレイ氏が1991年に創始し、1993年に発表した発達障害児に対するソーシャルスキルの支援方法です。これは、目に見えないソーシャル(社会的、社交的)な情報、世の中の暗黙のルールやコミュニケーションスキルを、文字や他の視覚的手段を使って明確にし、5W1H(Whenいつ、Whereどこで、Who誰が、What何を、Why何故、Howどうした)の答えとなる情報を自閉スペクトラム症の子供と周りの人間が共有することを目的としています。
ソーシャルストーリーの文章は平易な文章、読み手の人格を肯定する文体で書かれ、作成にはいくつかのルールがあります。
1、前向きで肯定的な文章
ソーシャルストーリーは「達成したことを賞賛する文章」を中心に構成され、前向きな表現を使います。例えば「〜してはいけません」という表現だと否定的な内容になってしまうので、避けます。また2人称(あなたは〜)は命令系の文章になりやすいので避け、1人称(私は〜)もしくは3人称(人は〜)といった俯瞰した形の文体を使います。
このように文章が与える印象にも気をつけながら、「出来たことを褒めてもらえる」ような文書が「出来ないこと指摘する」ような文章より多くなるようにします。これはソーシャルストーリーが対象の子供の「出来るようになったこと」の成長の記録になっていくからです。
2、導入部、主部、結論部で構成
話題の導入である「導入部」と、ストーリーの主な説明部分となる「主部」、ストーリーの締めとなる「結論部」の三部で構成され、前述の5W1Hに答える形式を取ります。
3、6つの文型を用いる
6つの文型を使い、事実説明文を入れた後、適宜他の文型を一つあるいは複数入れます。
○事実説明文(descriptive sentence)
一般的な事実を説明する
○心理説明文(perspective sentence)
知っていること、感じてること、考えていること
○自己指示文(directive sentence)
具体的なソーシャルスキルの内容(~しますという断言的な言い方は窮屈なので避ける)
○意味強調文(affirmative sentence)
文章の内容を肯定する
○協力説明文(cooperative sentence)
そのソーシャルスキルについて誰が何をサポートしてくれるか
○自己調整文(control sentence)
ストーリーを参考に本人が書き加える
あくまで本人を肯定的に書くので、自己指示文や自己調整文の合計より、事実説明文、心理説明文、意味強調文、協力説明文の合計が2倍以上になるようにします。
4、オーダーメイドのもの
発達障害のある子供は、言葉の裏にある意味を理解するのが苦手な場合があり、ソーシャルストーリーの文章は字義通りの表現に限られます。対象者の理解力に合わせ、簡単すぎず、難しすぎない表現を用いたオーダーメイドである必要があります。
場合によっては絵や写真を付け加え、視覚的な情報により理解を促すこともありますが、それがあることで対象者の注意が本筋からズレないようには気をつけます。
また、タイトルも重要で、ソーシャルストーリーのルールを踏まえた内容で、「肯定的でわかりやすく、シンプルなもの」を選びます。
全体において、本人の行動を非難したり健常者の行動を無理強いしてはいけません。また、「〜しなければならない」と義務的にしてしまったり、ストーリーで対象者をコントロールするような内容にならないよう気をつけましょう。
ソーシャルストーリーの期待できる効果

ソーシャルストーリーは特定の状況での適切な行動やコミュニケーション方法を教えることにより、自閉症児の社会的なスキルや、自己認識を向上させる効果があります。具体的に得られる効果を見ていきましょう。
1、不安やストレスの軽減
新しい状況や変化に対する不安を、ストーリーで事前に理解しておくことで軽減できます。
2、新しい状況への適応
変化への適応や新しいルーチンの確立など、ストーリーを繰り返し読むことで定着できます
。それにより日常のタスクや活動がスムーズになります。
3、友情の構築
他の人とのコミュニケーションの取りかたや、友情の基本的なルールを教えることで、友達を作る支援をおこないます。
4、適切な行動とコミュニケーションの方針
特定の場所や状況での適切な行動やコミュニケーションの方法を教えることで、社会的な適切さを理解できるようサポートします。
これらの効果により、自閉症児の生活の質を向上させ、自己認識や社会的統合を促すのに役立ちます。
ソーシャルストーリーの実施方法

ソーシャルストーリーを効果的に使用する方法を手順に沿って見ていきましょう。
1、事前準備
対象者の状況や行動に合ったストーリーを選出もしくは作成します。例えば新しい環境での行動の仕方、人とのコミュニケーションの取りかた、新たなルーチンの確立などから選びます。
2、ストーリーの共有
対象者にストーリーを読み聞かせるか、一緒に読みます。ただ読むだけではなく、対象者と対話して、共有していくことが重要です。理解を深める為に、視覚的アプローチとして、絵や写真などを利用するのも効果的です。
3、反復と練習
ストーリーを何度も読むことで理解が深まります。場合によっては質問を投げかけたり、意見を聞いたり、具体的な機会を与えたりしてスキルの獲得を目指します。
4、応用
実生活の中でストーリーで学んだことを使い、理想的な行動やコミュニケーションの実践をします。これを継続的に状況に合わせておこなって、フィードバックからストーリーの修正、新たな作成など、供給を続けます。
また、ソーシャルストーリーを日常生活に組み込むには次のような方法を取ります。
○学校
教室のルール、友達の作り方、授業の進行などに適用し、場面に合った行動の仕方を理解させることができます。
○家庭
日常のルーチン、例えば入浴の仕方や寝る前の準備など、兄弟の遊び方や家族間のコミュニケーションの取りかたなど、対応するストーリーを使います。
○公共の施設
公共の公園での遊び方や、買い物の仕方など、外出時にも自信を持って行動できるように支援します。
○日常生活
朝の準備や学校からの帰宅方法、宿題のやり方などに適用していくと、予測可能性が高まるのでストレスなく適切な行動が取れるようになります。
まとめ

ソーシャルストーリーは自閉症児が日常生活に自信を持ち、コミュニケーションスキルや社会的な行動を身に着ける為に非常に効果的です。一人一人に合わせた方法で、より良い生活を送れるよう、サポートしていきましょう。
療育キャリアではひとりひとりの希望に合った福祉関係の仕事を紹介しています。
登録は無料で簡単に行えますので、是非お気軽にご相談ください。
この記事の関連記事
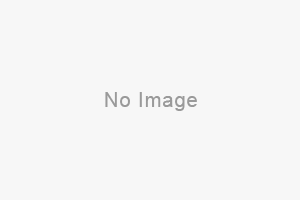
療育現場への転職のリアルって?現状や求められるスキルを徹底解説
療育現場への転職は、専門知識とコミュニケーション能力が必要で…
療育現場への転職は、専門知識とコミュニケーション能力が必要で…
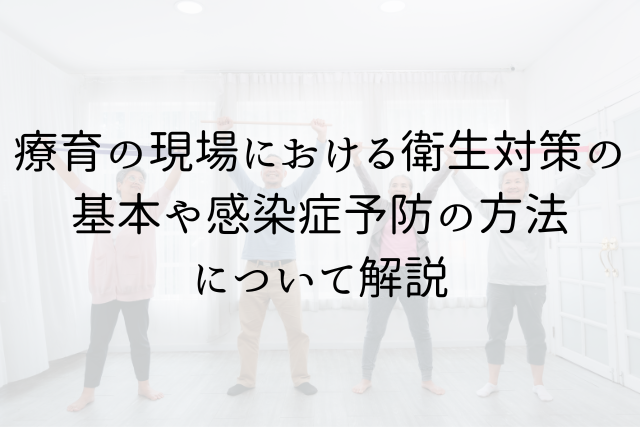
療育の現場における衛生対策の基本や感染症予防の方法について解説
「福祉の仕事をしたいけど、療育現場の衛生管理ってどんな…
「福祉の仕事をしたいけど、療育現場の衛生管理ってどんな…
とは?期待できる効果や実施方法について紹介.png)
療育におけるマカトンサイン(療法)とは?期待できる効果や実施方法について紹介
福祉の仕事について調べていると、たまに目にする「マカト…
福祉の仕事について調べていると、たまに目にする「マカト…

ムーブメント教育・療法とは?期待できる効果や実施方法について紹介
福祉の仕事について調べていると、時折目にする「ムーブメ…
福祉の仕事について調べていると、時折目にする「ムーブメ…

療育におけるインリアルアプローチとは?期待できる効果や実施方法について紹介
福祉の仕事について調べていると、目にすることがある「イ…
福祉の仕事について調べていると、目にすることがある「イ…

療育におけるソーシャルストーリーとは?期待できる効果や実施方法について紹介
福祉の仕事について調べていると、時折目にする「ソーシャ…
福祉の仕事について調べていると、時折目にする「ソーシャ…

療育におけるポーテージプログラムとは?期待できる効果や実施方法について紹介
皆さん「ポーテージプログラム」という言葉をご存じですか…
皆さん「ポーテージプログラム」という言葉をご存じですか…
とは?期待できる効果や実施方法について紹介.png)
療育における絵カード交換式コミュニケーションシステム(PECS)とは?期待できる効果や実施方法について紹介
福祉の仕事を調べていると目にすることがある、絵カード交…
福祉の仕事を調べていると目にすることがある、絵カード交…











