療育における絵カード交換式コミュニケーションシステム(PECS)とは?期待できる効果や実施方法について紹介
コラム
2023/12/19
とは?期待できる効果や実施方法について紹介.png)
福祉の仕事を調べていると目にすることがある、絵カード交換式コミュニケーションシステムという言葉。詳しく知りたいという方の為に、この記事ではどういうものか、その期待できる効果と実施方法まで、詳しく解説していきます。
もくじ
絵カード交換式コミュニケーションシステム(PECS)の期待できる効果
絵カード交換式コミュニケーションシステム(PECS)の実施の仕方
絵カード交換式コミュニケーションシステム(PECS)とは

Picture Exchange Communication Systemの略称で、絵カードを使ったユニークな代替、拡大コミュニケーション方法で、自閉症やその他のコミュニケーション障害がある子供や成人が自発的なやり取りを身につける為の学習方法として、1985年にアメリカのデラウェア州で開発されました。
そのトレーニングマニュアルは既に14か国語で翻訳、75か国以上で使用されていて、教師や施設職員、家族などでも簡単に作成でき、様々な場面で活用できるのが特長と言えます。
対象になるのは発語が困難であったり、他者とのコミュニケーションが困難な人ですが、発語は出来るが他者とのコミュニケーション目的では出来ない場合や、自分から能動的に他者に話しかけれない場合も対象になり、改善が目指せます。つまり、発語が出来ない人にとっては代替コミュニケーションの方法となり、発語が出来る人にとっては拡大コミュニケーションの方法となります。
対象者が候補者かどうか判断するためのフローチャートも公開されていて、チェックリストには次のような項目が挙げられています。(出典:ピラミッド教育コンサルタントオブジャパン株式会社)
○対象者は意味の通じるコミュニケーションをしている?
○そのコミュニケーションの仕方は普段あまり接しない人でもわかる?
○対象者はコミュニケーションを自発する?
○文章を長くするのに使えるかもしれない?
○語彙を増やすのに使えるかもしれない?
質問項目を順にチェックしていき、「いいえ」がつくかどうかで必要性を知ることができます。
絵カード交換式コミュニケーションシステム(PECS)の期待できる効果

欲しい物ややりたいこと、対応する人を要求するための方法を社会的な関わりを促しながらやり取りをおこなえるように段階を踏んで教えて行くことが特長で、応用行動分析の概念を基盤に、自発的な欲求を教えるところからはじめ、質問の受け答え、出来事についてコメントすることなどを段階的に進めていきます。
具体的に実証された効果としては、未就学の自閉スペクトラム症の子供に対して導入した場合、発語を始める事例が多いという報告があります。また、成人に対して導入した場合でも様々な効果が得られ、当初は幼い自閉スペクトラム症の子供を対象に開発されましたが、今では様々な知的障害を持った人、四肢不自由者、コミュニケーション障害のある幅広い年齢の人々に拡大、代替コミュニケーションシステムとして使用されています。
絵カード交換式コミュニケーションシステム(PECS)の実施の仕方

6つの指導段階で構成されていて、絵カードを使ったやり取りを自発的、持続的におこなうことからはじまります。段階的に絵カードのの弁別、文章や言葉を使用したやり取りに進んでいき、最終的には質問に対して自発的なコメントが出来ることを目指していきます。6つの指導を段階ごとに見ていきましょう。
1、コミュニケーションの仕方
対象者が本当に欲している物(やりたいこと)を絵柄にしたカードを用意し、療育者がこれを提示するところからスタートします。対象者は欲しい物をもらう為に、このカードを拾い、療育者に渡します。これを受けて、療育者はその物の名前を言いながら対象者に交換で実物を渡します。これは必ず、「対象者が自発的に行動してから交換する」ということに気をつけておこなわれる必要があります。
つまり、この段階では対象者が「カードを渡すと欲しい物がもらえる」ということを学ぶのが目的になります。やり取りを自発的におこなうのが目的なので、この時点で絵カードの意味を理解していなくても、区別出来ていなくても問題ありません。身体プロンプターも加えた2人の支援者でおこないます。
2、距離と持続性
この段階では、前段階で学んだ内容を般化、つまりどんな場面でも応用できる状態にします。用意した絵カードを「コミュニケーションブック」に貼り付け、置く場所を対象者から様々な距離に変更します。絵カードを渡す療育者も対象者からの距離を様々に変更し、対象者が自ら移動してカードを拾い、交換しにいくようにします。
療育者は対象者にこれらのことを持続的におこなうように指導しますが、この段階でも絵カードの意味の理解や区別は出来ていなくても大丈夫です。
3、絵カードの弁別
対象者が2枚以上の絵カードの中から、自分が欲しい物を弁別し、選択できることを目標にしていきます。
「コミュニケーションブック」をマジックテープのついたバインダーで作り、絵カードを並べたり、取り外しが簡単に出来るようにします。対象者はその中から自分の欲しい物の絵柄のカードを選び、段階的に欲しい物の絵柄を違う絵柄にしても弁別出来るように進めます。
4、文構成
欲しい物の絵カードと「ください」と書かれたカード(文カード)を繋げて、簡単な文書を作ります。
はじめは「ください」のカードは予めコミュニケーションブックに貼り付けておき、そこに欲しい物の絵カードを置くことからスタートします。次に絵カードと「ください」カード両方をブックに貼り付ける、「ください」カードを指さすことへ、段階的に指導します。この時、「ください」カードに合わせて、療育者は「ください」と読み返してある程度発語を促しますが、強制しないように注意します。
5、応答による要求
療育者の「何が欲しいですか?」という質問に絵カードと文カードを使って答えることを目指します。
はじめは質問と共に文カードを指さす身振りをして、例えば「ください」であれば欲しいものを聞かれていることを伝えますが、段階的にそれも外していき、様々な質問に答えられることを目指します。
6、コメント
周囲で起きた事柄にコメント出来るようになることを目指します。
「何が見える?」、「何が聞こえる?」、「これは何?」などの質問に対して「見えます」、「聞こえます」、「感じます」、「です」など述語を使って文章を構成することを学びます。
まとめ

自発的なコミュニケーションを育むことができる画期的な学習方法だということが、おわかりいただけたと思います。簡単に低コストで作成することも可能ですが、カリキュラムに沿って段階を踏んでおこなうことが重要です。実際に実施する際は応用行動分析の概念もしっかり学んでからおこなうよう注意しましょう。
療育キャリアではひとりひとりの希望に合った福祉関係の仕事を紹介しています。
登録は無料で簡単に行えますので、是非お気軽にご相談ください。
この記事の関連記事
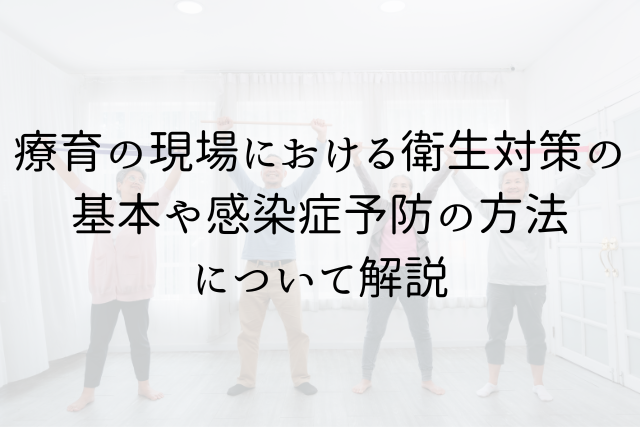
療育の現場における衛生対策の基本や感染症予防の方法について解説
「福祉の仕事をしたいけど、療育現場の衛生管理ってどんな…
「福祉の仕事をしたいけど、療育現場の衛生管理ってどんな…
とは?期待できる効果や実施方法について紹介.png)
療育におけるマカトンサイン(療法)とは?期待できる効果や実施方法について紹介
福祉の仕事について調べていると、たまに目にする「マカト…
福祉の仕事について調べていると、たまに目にする「マカト…

ムーブメント教育・療法とは?期待できる効果や実施方法について紹介
福祉の仕事について調べていると、時折目にする「ムーブメ…
福祉の仕事について調べていると、時折目にする「ムーブメ…

療育におけるインリアルアプローチとは?期待できる効果や実施方法について紹介
福祉の仕事について調べていると、目にすることがある「イ…
福祉の仕事について調べていると、目にすることがある「イ…

療育におけるソーシャルストーリーとは?期待できる効果や実施方法について紹介
福祉の仕事について調べていると、時折目にする「ソーシャ…
福祉の仕事について調べていると、時折目にする「ソーシャ…

療育におけるポーテージプログラムとは?期待できる効果や実施方法について紹介
皆さん「ポーテージプログラム」という言葉をご存じですか…
皆さん「ポーテージプログラム」という言葉をご存じですか…
とは?期待できる効果や実施方法について紹介.png)
療育における絵カード交換式コミュニケーションシステム(PECS)とは?期待できる効果や実施方法について紹介
福祉の仕事を調べていると目にすることがある、絵カード交…
福祉の仕事を調べていると目にすることがある、絵カード交…

療育における食事療法とは?期待できる効果や実施方法、注意点について紹介
福祉の仕事について調べていると、療育分野において時折目…
福祉の仕事について調べていると、療育分野において時折目…











