療育におけるマカトンサイン(療法)とは?期待できる効果や実施方法について紹介
コラム
2023/12/19
とは?期待できる効果や実施方法について紹介.png)
福祉の仕事について調べていると、たまに目にする「マカトンサイン(療法)」という言葉。実際にどのようなものなのか、詳しいことを知りたいという方の為に、この記事では「マカトンサイン(療法)」とは、というところから、期待できる効果と実施方法を詳しく解説していきます。
もくじ
マカトンサイン(療法)とは

マカトンサイン(療法)とは、「マカトン法」という会話のできない聴覚障害や知的障害を持つ人を対象に作られた、意思疎通の為のコミュニケーション手段の中で使われる、手話のような動作によるサインです。
マカトン法は1972~1973年にイギリスの言語療法士であったマーガレット・ウォーカー、キャサリン・ジョンストン、トニー・コーンフォースの3名を中心に作られ、その3人の頭文字を取ってマカトン法(Makaton)と呼ばれています。
マカトン法では「動作によるサイン」と「線画によるマークやシンボルの表示」の2つの方法を、実際に言葉でも話ながらおこない、場合によってはその他のジェスチャーや表情、アイコンタクトなども取り入れ、多くの情報を相手に伝えることで、言葉の理解を補助します。これは、「実際に話しながらおこなう」ことで、目と耳からの情報が一致し、実際の口語文とマカトンサイン、線画が一致しやすいという特長があります。
マカトンサインはイギリスでは約450の語彙と11000の線画が用意され、日本でも330前後の語彙が使用できます。対象者のニーズやレベルにより調整して使用しますが、もともと子供や知的障害者に向けたものなので、手話よりも簡単でわかりやすく、意思の疎通ができれば1単語のみのコミュニケーションでも全く問題ありません。手話との違いを次に示します。
手話との違い
○単語が少なく、動作が簡略化されている
○動作と共に声を出す音声同時提示
○ジェスチャーのように実際の動きに似ている
○手話は1語を2つ以上の動きで表すものも多いが、マカトンサインは基本1語を1動作
○手話は一般的な知能レベルの人が使うがマカトンサインは子供や知的障害者向け
このように、使用に当たって知的レベルを問わないので、現在は知的障害者、自閉症者やダウン症者など、障害をもつ人にも多く利用され、発達初期の子供へのコミュニケーション方法や、発達に遅れがある子供への言語と文字の理解を促す為にも注目されています。
マカトンサイン(療法)の期待できる効果

マカトンサイン(療法)を子供やコミュニケーションに困難がある人に実施することで得られる効果を順に見ていきましょう。
1、コミュニケーションの促進
言語障害やコミュニケーションの困難を抱える人にとって、マカトンサインを使ったコミュニケーションは手話よりも簡単で非常に直感的でわかりやすく、効果的なコミュニケーション手段となります。
2、言語発達の支援
マカトンサインは子供の言語発達において有益です。言語の基本的な要素や構造を理解しやすくして、言語の獲得を促進することができます。
3、非言語コミュニケーションの向上
マカトンサインはサインと同時に言葉でも情報を伝えますが、基本的には非言語のコミュニケーション手段として使用されるため、言葉だけでなく、ジェスチャーや表情を通じて情報を伝えることができます。これにより、豊かで効果的なコミュニケーションが可能になります。
4、社会参加の促進
マカトンサインは、言語障害やコミュニケーションに困難を抱える人々が社会に参加しやすくなる手段となります。他者との交流やお互いの理解の度合いが向上し、孤立感の軽減を期待できます。様々な人と交流し、活動への参加のきっかけになります。
5、教育のサポート
学校や教育機関へのマカトンサインの導入は言語障害のある人や、知的障害を持つ人など異なるコミュニケーションのニーズが求められても、サポートの手助けになります。また、同じサインを共有することで、コミュニケーションの円滑化が期待できます。
このように、様々な効果が期待でき、その特性から導入も簡単におこなえます。重要なのは個々の状況やニーズをしっかり把握して、それに見合ったサポートやアプローチをおこなうことです。
マカトンサイン(療法)の実施方法

マカトンサインの実施の際に重要なポイントや手順を紹介します。順に見ていきましょう。
1、サインの学習
まずは日常生活でよく使う言葉のサインを覚えるところからスタートしましょう。
わたし:自分を人差し指で指さします
あなた:相手を指さします
ありがとう:右手の手とうを上げ、相手を拝むような仕草、左手を添えます
ごめんなさい:手とうをチョップするように下におろす
トイレにいきたい:右手中指で左肩を上下する
飲み物が欲しい:手でコップの形をつくり、飲むような仕草で上下する
お父さん:親指を立てます
お母さん:小指を立てます
一緒に:両手の人差し指をくっつけてから前に出します
行く:対象となる方向を指さします
車(バス、トラック):車のハンドルを回す仕草
寝る:両手の平を合わせ、顔を傾けた横に添えます
例えばこれらを組み合わせると、「わたし」+「車」+「行く」=「私は車で行きます」だったり、「お父さん」+「一緒に」+「寝る」=「お父さんと一緒に寝る」のように文書を組み立てることができます。まずは日常生活でよく使うものから覚えて、繰り返し使っていくと効果的でしょう。
他にも、脳性マヒなどにより、サインを使うのが身体的に難しい場合でも「線画」を使ってマークやシンボルを表示する、もしくは指さしてもらうなどで、コミュニケーション困難者が自発的に意思表示をすることができますし、意思の疎通が容易におこなえるようになります。
2、ジェスチャー、表情との組み合わせ
サインと言葉だけでなく、手以外の部分も使ったジェスチャーや、表情でも情報を伝えると様々な組み合わせができ、より豊かなコミュニケーションができます。
3、使用環境の確認
マカトンサインを使用する環境によっては、特定のサインが好まれる場合があります。例えば、学校や施設などで、統一したサインを使うようにするとコミュニケーションが円滑になります。適したものを使うように心がけましょう。
4、専門家の指導を受ける
専門のトレーナーによる指導やトレーニングプログラムを受けることによって、マカトンサインを正確に理解することができます。指導者からのフィードバックを元に理解を深めましょう。
まとめ

マカトンサイン(療法)について詳しく見てきましたが、会話のできない人とも意思疎通ができるようになる、画期的なものだとおわかりいただけたと思います。サインを覚える努力は必要ですが、使いこなせるようになれば、たくさんの情報をわかりやすく相手に伝えることができますし、意思の疎通が難しかった相手とも理解しあえる可能性があります。使いこなせるようになれば、会話が出来なくても様々な活動に参加でき、支援の輪も広がっていきますので、是非チャレンジしてみてください。
療育キャリアではひとりひとりの希望に合った福祉関係の仕事を紹介しています。
登録は無料で簡単に行えますので、是非お気軽にご相談ください。
この記事の関連記事
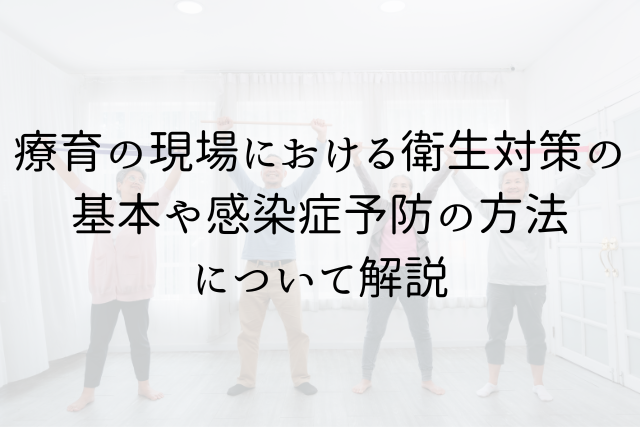
療育の現場における衛生対策の基本や感染症予防の方法について解説
「福祉の仕事をしたいけど、療育現場の衛生管理ってどんな…
「福祉の仕事をしたいけど、療育現場の衛生管理ってどんな…
とは?期待できる効果や実施方法について紹介.png)
療育におけるマカトンサイン(療法)とは?期待できる効果や実施方法について紹介
福祉の仕事について調べていると、たまに目にする「マカト…
福祉の仕事について調べていると、たまに目にする「マカト…

ムーブメント教育・療法とは?期待できる効果や実施方法について紹介
福祉の仕事について調べていると、時折目にする「ムーブメ…
福祉の仕事について調べていると、時折目にする「ムーブメ…

療育におけるインリアルアプローチとは?期待できる効果や実施方法について紹介
福祉の仕事について調べていると、目にすることがある「イ…
福祉の仕事について調べていると、目にすることがある「イ…

療育におけるソーシャルストーリーとは?期待できる効果や実施方法について紹介
福祉の仕事について調べていると、時折目にする「ソーシャ…
福祉の仕事について調べていると、時折目にする「ソーシャ…

療育におけるポーテージプログラムとは?期待できる効果や実施方法について紹介
皆さん「ポーテージプログラム」という言葉をご存じですか…
皆さん「ポーテージプログラム」という言葉をご存じですか…
とは?期待できる効果や実施方法について紹介.png)
療育における絵カード交換式コミュニケーションシステム(PECS)とは?期待できる効果や実施方法について紹介
福祉の仕事を調べていると目にすることがある、絵カード交…
福祉の仕事を調べていると目にすることがある、絵カード交…

療育における食事療法とは?期待できる効果や実施方法、注意点について紹介
福祉の仕事について調べていると、療育分野において時折目…
福祉の仕事について調べていると、療育分野において時折目…











